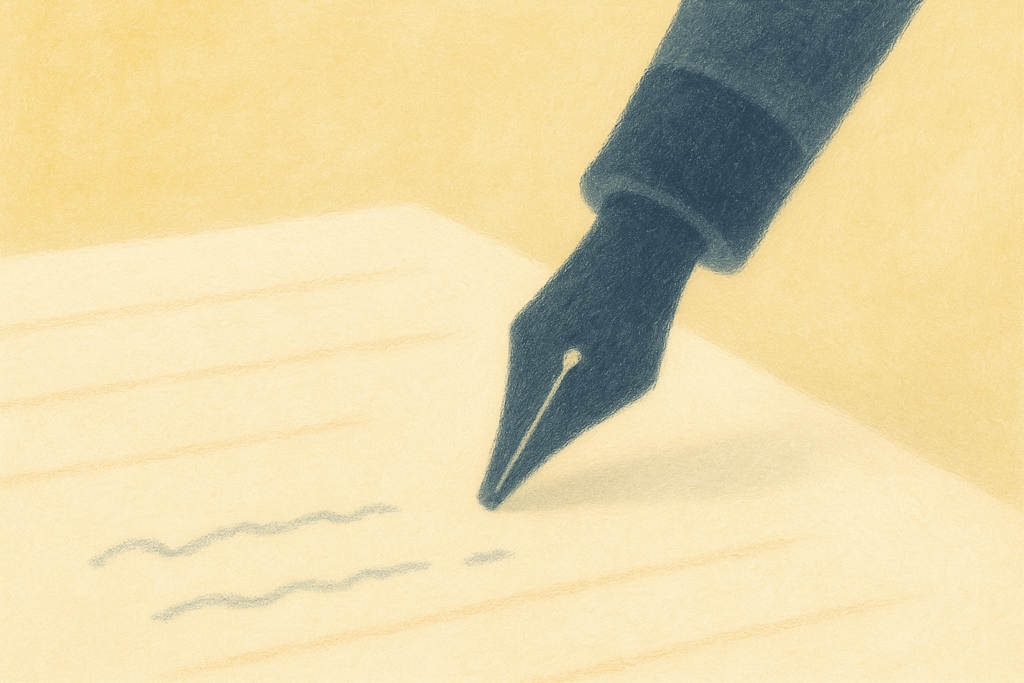
言葉のやりとりというのは人生のあらゆる場面で行われますが、医療現場というのは特に言葉のやりとりが難しい場所ではないかなと思います。まず医者というのは、医学を科学として学び、診療を行っています。すなわち、人間という肉体を科学的根拠に基づいてアプローチし、そこから得られた情報を患者様に伝えます。ただ病気の説明に100%こうだと言い切れるものはなく、わずかでもリスクがあればそれを伝え、さらに検査を行うように促します。心の面から見ると常に不安を煽るようなコミュニケーションであり、人によっては病院に行き始めたことで病気への意識と不安が強まり、病院通いから抜け出せなくなるということもあるかもしれません。
ここでお話したいのは、医者がどのような思いで患者様に病気の説明をしているかということです。ただ科学的根拠に基づいて情報を伝えているだけなのか、あるいは医療者自身が訴えられないようにするためにどのような些細なリスクも説明しようとしているのか、いずれも医療者の行っていることは間違いではなく、むしろ正しいと言えるでしょう。ただ患者様の心を考えたときには、もっと別の伝え方があるのではないかと思うのです。この事実やリスクを伝えたとき患者様はどのように思われるだろうか。そうしたことに思いを馳せているだろうか。同じ事実であっても、伝え方によって患者様の受け止め方はかなり違います。私自身、ある整形外科の疾患にかかったとき、整形外科医の友人らが多くいたので、彼らに同じ質問をしたことがあります。すると、まさにここに述べた通りで、一つの疾患に対する説明の仕方が全然違うんです。すごく不安になる助言もあれば、ただ医学的事実のみ教えてくれる助言もあれば、心を軽くしてくれるような助言もありました。前者の二人は医者としてこれまで学んできたことをそのまま実践しているのだと思います。最後の一人は患者様の病気だけを見ているのではなく、患者様を人として見ており、その心を見ているのだと思います。病院に来るまでに「今日は先生に何と言われるだろうかって不安だったんじゃないだろうか。それであれば安心できるように話をしないとね」とか「病院に来るだけでも大変だったかもしれないけれど、それでもよく来てくれましたね」とか、医者自身がそのような思いで患者様に接したならば、その言葉は自ずと優しくなり、美しい言葉になるんじゃないかなって思います。正しければいいのではないかではなく、「医は仁術なり」という言葉がありますが、患者様は病気を持った存在ではなく、病気とともに心を持った存在であり、その心が病気に、そして人生にどれほどの影響を与えるのかといったことに心を向けることが大切です。もし患者様の立場に思いを馳せて語ることができたならば、そのことによって気持ちが救われ、病気とわかっても前向きに生きられる人がいるのではないかと思います。
あと語り手の「信念」ですね。同じ言葉であっても信念をもって語る人の言葉の響き方は違います。心の医療においても「信念」が大事だと思うことがあります。私たちは本当に難しい心の状態の患者様に出会いますし、その心の持ち方はその人の自由なのでいろいろな角度からアプローチをしても全くこちらの言葉が入らないことがあります。そんなときには、やむを得ず寄り添っていくしかできないこともあります。ただその一方で、医者自身がどのような信念でかかわっているかというがこと患者様に大きく影響することもあります。例えば、「この人はどうしようもないのではないか」「良くなることなどないのではないか」と思われる患者様であっても、この人の心の奥には本当の自分があり、絶対に良くなる可能性があるはずだと信じてかかわっていると、奇跡のように信じられない変化を見せてくれる患者様もいます。信じると言っても、抽象的でわかりにくいかもしれませんね。信じるというのは例えば、その人の病気が治って笑顔になっているシーンをイメージできるかということに置き換えてもいいかもしれません。こうしたイメージは信じていなければ、思い浮かびません。「どうしようもないのではないか」と揺れる自分の心に打ち勝たなければ、イメージできません。ですから、イメージできたならば信じる力も強くなっているはずであり、信念をもって語りかけることができるようになります。信念を持って語る言葉というのは、目先の医学的な症状をどうこうするというレベルを超えて、どこか相手の心に響き、本当の自分に目覚めていくことに役立っていくように思います。
最後は、語り手の心の「波動」ですね。語り手の心が純粋で、穏やかで、愛に満ちた高い波動を持っているならば、その言葉はなぜか染み入るように心に伝わるのではないかと思います。他の人の言葉は心に響かないのに、なぜかこうした語り手の言葉は心の中に入ってきます。人のことを何とも思っていないような人が、立派な言葉を語っても上っ面だけで何も伝わりませんが、波動の高い愛に満ちた人が語るならば、その言葉は相手の心に染み入り、人生を好転させるきっかけになるのではないかと思います。
このように言葉というのは、単に情報を伝えるためだけの手段ではありません。そこに語り手の持つ様々な心の要素が加われば、人の心に光を灯すようなコミュニケーション手段に変わっていくのではないかと思います。
月刊 『公営企業』 | 一般財団法人 地方財務協会
https://www.chihou-zaimu.com/koueikigyo